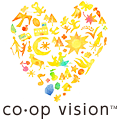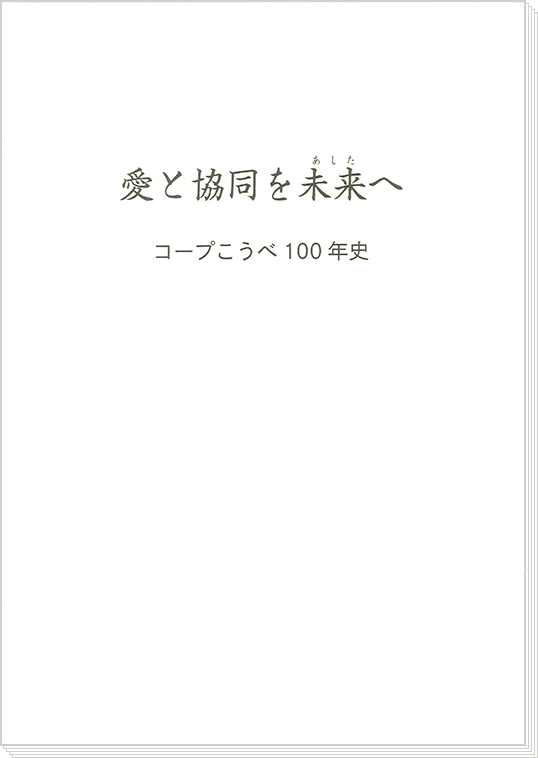100年先にも伝えたい私たちの物語

1921

「愛と協同」の精神を原点に
1921年、生協の父・賀川豊彦指導のもと、コープこうべの前身となる神戸購買組合と灘購買組合が相次いで誕生しました。一人ではできないことも、みんなの力を合わせれば願いや夢をかたちにできる。コープこうべは「愛と協同」の精神を原点にスタートしました。
1921
- 1921年 4月
-
神戸購買組合創立
(1924年神戸消費組合に改称)
1921
- 1921年 5月
-
灘購買組合創立
(1935年灘購買利用組合に改称)
1921

荷車や自転車で配達
現在の地域担当(宅配事業)につながる「御用聞き」を、創立当初から行っていました。隔日または3日に1度訪問して注文を聞き、当日もしくは翌日に配達するという制度で組合員に支持されていました。
1923

自分たちが望むものを自分たちの手で
1923年、灘購買組合が甲東村(現・西宮市)にしょうゆの醸造工場を開設。翌1924年から供給を開始。
「自分たちが本当に望むものを、自分たちの手で作りたい」という願いを実現しました。その想いは「六甲アイランド食品工場」へと受け継がれており、生産品目を見直しながら商品の開発や改善に取り組んでいます。1925年に始まった餅づくりは、現在も続く年末の風物詩です。
1923
- 1923年
- 灘購買組合が醸造工場を開設し、しょうゆの醸造を開始
1924

生協の女性組織の誕生
1924年7月、神戸消費組合で生協における日本最初の女性組織「家庭会」が誕生。協同組合の学習、料理や洋裁など生活の向上をめざした教え合いが展開されました。組合員活動の原点です。
1924
- 1924年 7月
- 神戸消費組合に「家庭会」が誕生
1929
- 1929年 7月
- 灘購買組合に「家庭会」が誕生
1931
- 1931年 2月
- 灘購買組合が芦屋にセミセルフサービス方式の第1号店をオープン
1938
- 1938年 7月
- 阪神大水害が発生
1945
- 1945年 8月
-
第二次世界大戦終戦。
空襲で事業所の大半を失うが、戦後すぐに事業を再開
1945
- 1945年 11月
- 日本協同組合同盟(現・日本生活協同組合連合会)創立
1947

播磨生活協同組合の前身が誕生
1947年11月、播磨生活協同組合の前身である「播磨造船所購買利用組合」が誕生。播磨造船所で働く従業員のくらしを守る職域生協として発足し、1985年に地域生協に転換。地域の組合員に密着した活動を展開していきました。(1995年4月コープこうべと合併)
1947
- 1947年 11月
-
播磨造船所購買利用組合創立
(1960年播磨生活協同組合に改称)
1949
- 1949年 7月
- 灘購買利用組合に「四ツ葉会」(家事サービスグループ)が誕生
1949
- 1949年 10月
- 「消費生活協同組合法」により灘購買利用組合が「灘生活協同組合」に改称
1950

大阪北生活協同組合の前身が誕生
1948年、大阪府豊中市で女性たちによる共同購入の仕組み「土曜会」が始まりました。
2年にわたる活動を経て「生協は福祉でなければならない」「みんなが幸せになる生協をつくろう」と、1950年1月に大阪北生活協同組合の前身である「豊中睦(むつみ)生活協同組合」が誕生しました。(2011年4月大阪北生協はコープこうべと合併)
1950
- 1950年 1月
- 豊中睦生活協同組合創立(1967年大阪北生活協同組合に改称)
1950
- 1950年 1月
- 「消費生活協同組合法」により神戸消費組合が「神戸生活協同組合」に改称
1952

世界の生活協同組合と手をつなぐ
1952年3月、日本生活協同組合連合会(日本生協連)は第二次世界大戦前に脱退した国際協同組合同盟(ICA)への復帰がようやく認められました。
※ICA…1895年設立。後に国連に登録された世界最大のNGO。世界109ヵ国から311協同組合組織が加盟。組合員総数は12億人を超える。(2019年8月現在)
1952
- 1952年 3月
- 日本生活協同組合連合会(日本生協連)が国際協同組合同盟に加盟
1952
- 1952年
-
「メロンパン(現・神戸ハイカラ
メロンパン)」が誕生
1958
- 1958年 9月
- 生協霊園(芦屋市霊園内)を開設
1959

組合員と職員の想いをカタチに
1959年12月、シロップに人工甘味料ではなく砂糖を使用した缶詰「生協のみかんシラップ漬」が誕生しました。安全・安心を求める組合員の声と、良いものを提供したいという職員の想いがカタチになったコープ商品の第1号です。
1959
- 1959年 12月
- コープ商品第1号「生協のみかんシラップ漬」が誕生
1961
- 1961年 2月
- 灘生活協同組合が初のスーパーマーケット「くみあいマーケット芦屋店」をオープン
1961
- 1961年 5月
- 国鉄(現・JR)住吉駅前に本部会館を開設し、1・2階に「くみあいマーケット住吉店」をオープン
1962
- 1962年 4月
-
「灘生活協同組合」と「神戸生活協同組合」が合併し「灘神戸生活協同組合」に
1962
- 1962年 4月
- 機関紙『協同』(現・『きょうどう』)創刊
1967
- 1967年 1月
- 組合員が10万人に
1967
- 1967年 5月
- 無漂白小麦粉を使った食パンの製造を開始
1967

安全・安心はみんなの願い
1967年10月、全国の生協では初めて、独自の商品検査室を開設。当時、農薬や食品添加物の安全性が問題になっており、「安全な食品が欲しい」「安心して食べたい」という組合員の切実な声に応え商品検査活動をスタートしました。
2017年に50周年を迎え、開設日である10月1日は「商品検査の日」として認定されています。
1967
- 1967年 10月
- 「商品検査室(現・商品検査センター)」を開設
1969

自分たちで守る食の安全・安心
当時、うどんの製造に殺菌料として多用されていた過酸化水素に、人体への悪影響の疑いが持たれ始めていました。数カ月に及ぶ検査(※)の結果、1969年9月に食品工場で製造するうどんへの過酸化水素の使用をやめ、加熱殺菌法に切り替えました。
※過酸化水素のうどんへの残留検査や、殺菌効果を発揮しながら残留しない方法を検討
1969
- 1969年 9月
- うどんの製造に「過酸化水素(殺菌料)」使用を中止
1970
- 1970年 7月
- 組合員が20万人に
1970
- 1970年 9月
- コープの産直第1号「更別村メークイン」が誕生
1971
- 1971年 7月
- 「コープベル(現・コープこうべ くらしの情報センター)」を開設
1972

くらしの中から環境を考える
1960年代の合成洗剤による泡公害や水質汚染などの問題を機に、1972年7月、生協推奨品として「田舎娘粒状せっけん」を開発。供給をスタートしました。1976年8月にはコープ商品として普及。洗剤の安全性を追求し水環境を守る取り組みは、1970~80年代に実施した「せっけん運動」「せっけんキャンペーン」へとつながりました。活動を通して組合員同士が学び合い、くらしの中で環境を考えるきっかけとなっていきました。
1972
- 1972年 7月
- 「田舎娘粒状せっけん」を開発
1973
- 1973年 10月
- 組合員が30万人に
1973
- 1973年 10月
- 食品工場で製造する豆腐へのAF2(殺菌料)使用を中止。翌1974年にはAF2を使用するすべての食品の取り扱いを中止
1973
- 1973年 10月
- 第一次オイルショック
1974
- 1974年 2月
- 「生活見直し運動」がスタート
1975
- 1975年 5月
- 「家庭会」と「運営委員会」を統合し「地域運営委員会」へ
1975
- 1975年 11月
- 組合員が40万人に
1976

子どもたちに学びと交流の場を
1976年8月、協力し合って何かを体験できる場を子どもたちに提供する目的で「虹っ子使節団」をスタート。コープの産直第1号であるメークインの産地・北海道更別村を訪問し、農家の子どもたちと交流しました。現在の「虹っ子スタディツアー」「虹っ子スクール」など、さまざまな取り組みにつながっています。
1976
- 1976年 8月
- 「虹っ子使節団」がスタート
1976
- 1976年 10月
- 店舗の名称を「コープ」に統一
1977
- 1977年 10月
- 週1回訪問、予約カードシステム(現・『めーむ』)で協同購入制度を開始
1977
- 1977年 11月
- 「OPP(防かび剤)不使用レモン・グレープフルーツ」の取り扱い(輸入)を開始
1978

安全と健康を最優先
当時、食パンづくりにパン生地改良剤として広く使用されていた「臭素酸カリウム」に、発がん性の疑いがあるということがわかりました。
そこで、組合員の安全と健康を守るために「疑わしきは使用せず」の考え方を貫き、1978年2月に全国で初めてパン生地への「臭素酸カリウム」の使用を中止。その後、全国の生協へと広がりました。
1978
- 1978年 2月
- 食パン製造で「臭素酸カリウム(パン生地改良剤)」使用を中止
1978

買い物袋から環境を考える
第一次オイルショックの後、省資源活動の一環として、店舗のサービスで提供していた包装紙類の節約を呼びかけました。1974年の「コープバッグ(エコバッグ)」のテスト使用を始め、1978年5月からは買い物袋再利用運動がスタート。1991年には、スタンプ還元制度の対象をどんな袋でも利用可とする「買い物袋持参運動」へ発展しました。
1978
- 1978年 5月
- 「買い物袋再利用運動(スタンプ制)」がスタート
1978

平和活動を広げる
1978年8月6日「核兵器完全禁止・被爆者援護世界大会・広島大会」に初めて参加。1981年の「原水爆禁止・被爆者援護ヒロシマ集会」には組合員の親子代表団170人を派遣しました。これをきっかけに「100円カンパ」がスタート。現在も「平和のカンパ」として続いています。
1978
- 1978年 8月
- 原水爆禁止世界大会に参加
1978
- 1978年 10月
- 第二次オイルショック
1980
- 1980年 3月
-
神戸市と「緊急時における生活物資確保のための協定」を締結
(2021年3月末現在:27市11町と同様の協定を締結)
1980
- 1980年 6月
- 組合員が50万人に
1980
- 1980年 9月
- 組合員のくらしを守る助け合いの活動として全労災と提携し、「コープ共済」の取り扱いを開始
1981
- 1981年 6月
- 「せっけんキャンペーン」がスタート
1981
- 1981年 7月
- 「100円カンパ(平和のカンパ)」がスタート
1982
- 1982年 5月
- 生活文化センターを開設
1982
- 1982年 6月
- 「ユニセフ募金活動」がスタート
1982
- 1982年 9月
- 「レインボースクール(ミニ学習会)」がスタート
1982
- 1982年 9月
- 「排水チェック運動」がスタート
1983
- 1983年 3月
- 鳴尾浜配送センターを開設
1983

できるときに、できる人が、できることを、お手伝い
1983年6月、「地域に相互扶助の輪を」という趣旨で有償の家事支援活動「コープくらしの助け合いの会」がスタートしました。
当初は高齢の組合員を対象に話し相手や食事づくり、買い物や掃除など、ちょっとした家事を手伝う活動でした。その後、高齢者だけでなく、体が不自由な方や子育て中の方などの生活の自立を支える活動へと発展しました。この組合員同士の支え合い活動は、全国の生協などへ広がっていきました。
1983
- 1983年 6月
- 「コープくらしの助け合いの会」がスタート
1984
- 1984年 3月
- 助け合い制度「コープむつみ会」がスタート
1986
- 1986年 6月
- 兵庫県・阪神7市1町と共同出資し、重度障害者多数雇用事業所「阪神友愛食品株式会社」を設立
1987
- 1987年 9月
- 「新、衣・食・住 。COOP・STYLE」供給を開始
1987
- 1987年 11月
- 六甲アイランド食品工場で一部の部門が稼働。翌1988年旧工場からの移転が完了し本稼働
1988
- 1988年 4月
- 「コープふれあい食事の会」がスタート
1989
- 1989年 1月
- 葬祭サービス事業「クレリ」を開始
1989
- 1989年 3月
- 生協初の複合業態店舗「シーア」をオープン
1990
- 1990年 3月
- 牛乳パックの回収がスタート(リサイクル回収の第1号)
1991
- 1991年 1月
- 組合員が100万人に
1991

創立70周年 シンボルマークも新しく
1991年4月、組合員100万人突破と創立70周年を機に「生活協同組合コープこうべ」に名称を変更。名称は公募により3万件の中から決定しました。シンボルマークには「人と人、組合員とコープこうべ、コープこうべと地域社会、コープこうべとなかまの生協、さらには世界。また、生活と生産、人と自然。手に手をとって、そのかなめとなっていく」という想いが込められています。ブルーとグリーンの色彩は、コープこうべをはぐくむ海と山、そして私たちの未来と安らぎ、自然と生命を象徴しています。
1991
- 1991年 4月
- 「生活協同組合コープこうべ」に改称
1991

人と自然にやさしい食べものづくり
1991年4月、「人と自然にやさしい食べものづくり」をめざす「フードプラン商品」の供給がスタートしました。スウェーデン・ストックホルム生協が発表した「オルターナティブ・フード・プログラム(もうひとつの食べものづくり計画)」という構想をヒントに、「消費者にも、生産者にも、そして自然環境にもやさしい食べものづくり」をめざしています。
1991
- 1991年 4月
- フードプラン商品の供給を開始
1991
- 1991年 9月
- 「協同学苑」を開設
1991
- 1991年 10月
- 飲料缶・トレイ・ペットボトルの回収がスタート
1992
- 1992年 6月
- 「地域運営委員会」を「地域コープ委員会」に改称
1992
- 1992年 7月
- 活動エリアが兵庫県全域に拡大
1993
- 1993年 3月
- 社会福祉法人「協同の苑」を設立
1993
- 1993年 6月
- 「製造物責任(PL)法の早期制定を求める百万人請願署名」にコープこうべで約117万筆集まる
1994
- 1994年 6月
- PL法制定
1995

被災地に生協あり
1995年1月17日午前5時46分、阪神・淡路大震災が発生。本部ビルを始め18もの施設が全・半壊しました。被害総額は約500億円。甚大な被害の中で職員はもちろん、組合員や取引先、全国の生協など、多くの人たちが助け合い支え合って復興をめざしました。その姿は「被災地に生協あり」と評されました。
1995
- 1995年 1月
- 阪神・淡路大震災が発生
1995
- 1995年 2月
- 「創造的復興」を決意。コープボランティア本部を設置し、その後各地区に「コープボランティアセンター」を開設
1995

ゆるやかな連携・交流から合流へ
播磨生協は、1988年からコープこうべの協同購入システム導入やコープ商品を取り扱うなど事業間の連携、店舗運営や組合員活動の交流がスタート。1995年4月、正式に合併しました。
1995
- 1995年 4月
- 播磨生活協同組合と合併
1995
- 1995年 6月
- 「買い物袋持参運動」を拡大しレジ袋を有料化。翌1996年から名称を「マイバッグ運動」に
1995
世界の協同組合の道しるべ
国際協同組合同盟(ICA)が定めた「協同組合原則」に、1995年9月のICA100周年大会で第7原則として「コミュニティへの関与」が加わりました。これにのっとり「協同組合は組合員によって承認された政策を通じて地域社会(コミュニティ)の持続可能な発展のために活動すること」と明記されました。
協同組合原則は、世界で最初の生活協同組合といわれる「ロッチデール公正開拓者組合」が定めた「ロッチデール原則」が原点です。
1995
- 1995年 9月
- ICA大会(マンチェスター)で協同組合原則を改定
1996
- 1996年 2月
- 「(公財)コープともしびボランティア振興財団」を設立
1996
くらしを守る決意を言葉に
「くらしを守る」という生協の使命に沿った「ありたい姿・協働のあり方」を示すため、1996年に「コープこうべ環境憲章」、1997年に「コープこうべ福祉文化憲章」、1999年に「市民福祉社会への協働憲章」を定めました。環境憲章では、環境問題は持続可能な社会づくりをめざす生協運動の根本的課題であり、活動と事業の両面から取り組んでいく決意を表明。福祉文化憲章、市民福祉社会への協働憲章では地域での支え合い・助け合いの精神を育んでいく決意を表明しています。
1996
- 1996年 5月
- 第76期通常総代会で「コープこうべ環境憲章」を採択
1996
- 1996年 9月
-
「地震災害等に対する国民的保障制度を求める」署名運動がスタート。兵庫県内で435万筆(うちコープこうべで356万筆)集まる。
翌1997年2月には全国で2400万筆の署名を政府に提出。1998年5月成立の「被災者生活再建支援法」につながる
1996
- 1996年 11月
- 地震で全壊した「コープリビングセンター甲南」を、福祉の総合施設「は~とらんど」を併設した「コープリビング甲南」として復興オープン
1997
- 1997年 8月
-
新戸配システム「ひまわり」(現・個人宅配)を開始
1998
- 1998年 4月
- 在宅介護サービス事業を開始
1999
- 1999年 1月
- 阪神・淡路大震災を教訓に、国内外で大規模な自然災害などが発生した場合の迅速な支援を目的に「コープこうべ災害緊急支援基金(ハート基金)」を設立
2000

揺るぎない平和への想いを確認
平和の取り組みは1978年にスタート。「平和~母と子の願い~」をスローガンに、組合員とともに平和の活動をすすめてきました。1996年にはコープこうべ「平和の取り組み指針」を策定。2000年に明文化した「コープこうべ平和へのちかい」には、子や孫の世代も平和な世の中であって欲しいという組合員の願いと、平和の大切さ、尊さを受け継いでいこうという想いが込められています。
2000
- 2000年 5月
- 「コープこうべ平和へのちかい」を明文化
2000

自分たちで選ぶ、食の安全・安心へ
2000年8月、「食品衛生法の改正と充実強化を求める請願署名」運動がスタート。翌2001年3月には、約210万筆の署名が集まり(全国で約1400万筆)国会に提出しました。これを受け、2003年5月、多くの組合員の願いだった「食品安全基本法」制定と「食品衛生法」改正が相次いで実施されました。
2000
- 2000年 8月
- 「食品衛生法の改正と充実強化を求める請願署名」運動がスタート
2000
- 2000年 10月
- お買い物&コミュニティサイト「コープこうべネット」を開始
2001
- 2001年 4月
- 「Coop's(コープス)」商品の供給を開始
2001

創立80周年記念事業
2001年5月、限りある資源の循環を実践するためのモデル事業として「環境共生型農園エコファーム」を開設。店舗から出る野菜や肉の加工くずで堆肥を作り、その堆肥を使って農園で野菜を育て、できた野菜を店舗などで供給するという資源循環を実現しました。マイファームや体験農園など、組合員が土に触れる体験ができる場も提供しています。
2001
- 2001年 5月
- コープ土づくりセンターを併設した「環境共生型農園エコファーム」を開設
2002
- 2002年 4月
- 「めーむひろば」をコープミニ全店舗で開始
2002
- 2002年 4月
- 「子育てひろば」活動がスタート
2003
- 2003年 11月
- 畜産不正取引事件発覚
2003
- 2003年 12月
- 食品工場の産業廃棄物処理設備が稼働
2005
- 2005年 4月
- 「店舗ポイント制度」を開始
2006
- 2006年 12月
- 神戸市と「レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定」を締結。これを機に各自治体とレジ袋削減に関する協定を結ぶ(2021年3月末現在:23市6町)
2007
- 2007年 5月
- 59年ぶりに消費生活協同組合法改正法案が可決・成立。翌2008年4月1日施行
2007

「マイバッグ運動」が進化
2007年6月、食品を取り扱う全150店舗でレジ袋の代金をレジで精算する方式にしました。当時、コープこうべの事業規模や店舗数を持つ組織での一斉実施は、全国でも例を見ない先進的な取り組みでした。この「マイバッグ運動」の進化で、マイバッグ持参率は、それまでの約7割から約9割に上昇しました。
2007
- 2007年 6月
- マイバッグの持参率が約9割に
2007
- 2007年 10月
- マイバッグ運動の取り組みが評価され「平成19年度容器包装3R推進環境大臣賞(小売部門)」最優秀賞を受賞。コープこうべとエコファームを運営する(有)みずほ協同農園が「平成19年度食品リサイクル推進環境大臣賞奨励賞」を受賞
2008

兵庫県「企業の森づくり制度」第1号
2008年5月、兵庫県、西宮市、(社)兵庫県緑化推進協会とコープこうべの4者で「企業の森づくり」協定を締結。兵庫県「企業の森づくり制度」の第1号として、西宮市にある社家郷山(しゃけごうやま)で、森林整備と体験学習の場づくりをすすめています。この活動にはレジ袋代金を活用しており、木々が生い茂る森を太陽の光が届くように整備するなど、多様な生きものが暮らす里山をめざしています。
2008
- 2008年 11月
- 「コープの森・社家郷山」整備活動がスタート
2009

献身100年記念イベントを開催
1909年12月24日、21歳の賀川豊彦は神戸のスラム街で救済活動を始めました。それから100年となる2009年に「協同」の理念を再確認し、後世に伝えるため、講演会やパネルディスカッション、記念式典など「賀川豊彦献身100年記念事業」が東京と神戸で開催されました。
2009
- 2009年
- 賀川豊彦献身100年
2009
- 2009年 7月
- 改正生協法による県域規制の一部緩和を受け、京都府京丹後市へ活動エリアを拡大
2010

核兵器廃絶を訴える
2010年4月、ニューヨークで開催された核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に合わせ、生協代表団の一員としてコープこうべの組合員と職員がパレードや集会に参加。世界に向けて核兵器廃絶を訴えました。2015年の同会議の際にも参加しました。
2020年4月のNPTは、新型コロナウイルス感染症拡大のため、延期されました。
2010
- 2010年 4月
- 核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に合わせ生協代表団に2人を派遣
2010
- 2010年 9月
- コープス「ひょうご発」シリーズの供給を開始
2010
- 2010年 10月
- 西宮市から受託した「シニアサポート事業」を開始
2010
- 2010年 12月
- 行政の「見守り活動」に協力を開始。神戸市東灘区御影北部地区の高齢者見守りモデル事業に協同購入センター東灘が協力
2011

「たすけあい」の精神、東北へ
2011年3月11日に発生した東日本大震災の直後から、みやぎ生協を支援するため、のべ241人の職員を派遣。組合員の安否確認の手伝いや店舗の再開支援などを行いました。また地震の翌日に始まった組合員による緊急募金には、約4億円が集まりました。被災地のくらしに寄り添いながら、組合員同士の交流が続いています。
2011
- 2011年 3月
- 東日本大震災が発生。被災地への支援活動を開始
2011

合併をより大きな「協同の力」に
2011年4月、大阪北生活協同組合と合併。お互いの地域の個性を大切にしつつ、より大きな「協同の力」で助け合いの社会の実現に向けた活動と事業をすすめることを誓いました。合併によりコープこうべの組合員は167万人になりました。
2011
- 2011年 4月
- 大阪北生活協同組合と合併
2011

毎日お届け、くらしも応援!
2011年4月、くらしに安心を届けるサービスの一つとして夕食サポート事業「まいくる」がスタート。栄養バランスのとれた夕食を届けており、子育て中や仕事を持つ組合員にも支持されています。1食あたり0.5円を地域のボランティア活動に寄付しています。
2011
- 2011年 4月
- 夕食サポート事業「まいくる」を開始
2011
- 2011年 9月
- 福島第一原発事故の影響から食品中の放射性物質の自主検査を開始
2011

買い物が楽しい、おしゃべりも楽しい!
2011年10月、買い物に出かけるのが困難な組合員へのお役立ちを目的に「移動店舗」がスタート。コープの店舗の魅力をギュッと詰め込んだトラックが週に一度、決まった時間、決まった場所に訪問し、商品だけでなく買い物の楽しさもお届けしています。
2021年3月末現在、9台が稼働しています。
2011
- 2011年 10月
- コープ西宮北を拠点に「移動店舗」を開始
2012
- 2012年
-
国連が定めた「国際協同組合年」。
協同組合の役割や存在意義について再確認するイベントなどを神戸で開催
2012
- 2012年 7月
- 「福島の子ども保養プロジェクトinよしまキャンプ」を開催(神戸YMCA、兵庫県ユニセフ協会との共催)
2013
- 2013年 1月
- コープ西神南で「コープこうべネットスーパー」を開始
2013

とれぴち・とれしゃき
兵庫県が後援する地産地消事業として、2013年に兵庫県漁業協同組合連合会との協働事業「ひょうご地魚推進プロジェクト(とれぴち)」がスタート。
2015年には、 兵庫県、JAグループ兵庫と連携して「兵庫地場野菜振興プロジェクト(とれしゃき)」がスタートしました。
2013
- 2013年 7月
- 「とれぴち」を開始
2013
- 2013年 8月
- 障がい者の就労支援を目的に子会社「株式会社ゆうあいサポート」を設立。翌2014年4月から店頭で回収したペットボトルのプレス作業を開始
2013

再生可能エネルギーの取り組み
2013年9月、再生可能エネルギーの普及をめざして鳴尾浜配送センターに太陽光パネルを設置し、発電を開始しました。以降、コープこうべの事業所や地域企業施設の屋上などで太陽光パネルの設置を推進。エネルギーの地産地消の取り組みが始まりました。
2013
- 2013年 9月
- 鳴尾浜配送センターで太陽光発電事業を開始
2014
- 2014年 4月
- 子育て支援事業(学童保育)「Terakoya」東灘校を開校
2014
- 2014年 10月
- コープこうべキャラクター「コーピー」デビュー。名前は組合員に公募し投票により決定
2015
- 2015年 4月
- 協同学苑内に「コープこうべ安全運転センター」を開設
2015
- 2015年 4月
- 再生可能エネルギーを利用した「電力供給事業」をコープこうべの一部施設で開始
2015
- 2015年 9月
- 「とれしゃき」を開始
2015
- 2015年 9月
- 「第3回食と農林漁業の食育優良活動表彰 農林水産大臣賞」を受賞
2016
- 2016年 4月
- 熊本地震が発生。コープくまもとで復旧支援を行う
2016
- 2016年 6月
- コープこうべのオリジナル電子マネー「COPICA(コピカ)」を全店舗で導入
2016
- 2016年 7月
- 店舗・事務所に併設しないコミュニティースペースとして「コープのつどい場」づくりがスタート
2016

新たな買い物支援のカタチ
2016年10月、高齢者や小さな子どもがいる方など、普段の買い物に困っている組合員を対象に、自宅と店舗の間を無料で送迎する「買いもん行こカー」の実験運行がスタートしました。2021年3月現在、21台が稼働しています。
2016
- 2016年 10月
- コープデイズ神戸北町を拠点に「買いもん行こカー」を開始
2016
- 2016年 10月
- サービス付き高齢者向け住宅「コープは~とらんどハイム本山」を開設。1階には、ろっこう医療生協が運営する「にじいろクリニック」も開業。地域の総合福祉拠点に
2016

「協同組合」がユネスコ無形文化遺産に
2016年11月、「協同組合の思想と実践」がユネスコ無形文化遺産に登録されることが決定。決定にあたってユネスコは、「共通の利益と価値を通じてコミュニティづくりを行うことができる組織であり、雇用の創出や高齢者支援から都市の活性化や再生可能エネルギープロジェクトまで、さまざまな社会的な問題への創意工夫あふれる解決策を編み出している」としています。
2016
- 2016年 11月
- 「協同組合の思想と実践」がユネスコ無形文化遺産に登録
2017

「コンセントの向こう側」を考える
2017年4月、電力小売事業「コープでんき」スタート。地球の未来のことを考え、電源構成にこだわった電気(※)を供給しています。地元の太陽光発電所やバイオマス発電所から電気を調達するなど「電気の地産地消」もすすめており、電力事業を通して持続可能なエネルギー社会への転換をめざします。
※コープでんきの電源構成:再生可能エネルギー30%、天然ガス70%
2017
- 2017年 4月
- 「コープでんき」を開始
2017
- 2017年 4月
- サービス付き高齢者向け住宅「コープは~とらんどハイム本山」に、小規模型事業所内保育園「どんぐりっこ もとやま」を開設
2017
- 2017年 4月
- 宅配の商品カタログ『めーむ』の注文ができる「コープこうべアプリ」を開始
2017
- 2017年 4月
- 明石市から受託した「ファミリーサポート事業」を開始
2017
- 2017年 6月
- 「フードドライブ」の取り組みがスタート
2017

賀川豊彦の言葉を胸に
台風や豪雨、地震などの自然災害が相次ぐなか、被災地に寄り添った支援活動を実施しています。近年では「平成29年7月九州北部豪雨」の被災地に、ひょうごボランタリープラザと合同で復旧支援のボランティアバスを運行。被災家屋の泥出し、家具等の搬出、洗浄作業などを行いました。「平成30年7月豪雨」の被災地でもボランティア活動を実施しました。
2017
- 2017年 7月
- 平成29年7月九州北部豪雨が発生
2017
- 2017年 10月
- 鳴尾浜リサイクルセンターが稼働
2018
- 2018年 4月
- 「環境チャレンジ目標2030」を策定
2018

「CO・OP NEXT100」の取り組みが始動
2018年6月、創立100周年を迎えるにあたり、次の100年に向けてのプロジェクト「CO・OP NEXT100」を立ち上げました。組合員や役員・職員を挙げて、コープこうべのビジョン「ターゲット2030(に・まる・さん・まる)」づくりをすすめてきました。「2030年の地域のありたい姿、ありたいくらし、地域」について語り合い、「①人と人がつながり助け合える」「②持続的なまちと自然との共生」「③健康でいきいきとした毎日」「④みんなが安心できる」という、4つのテーマがまとまりました。
2018
- 2018年 6月
- 「CO・OP NEXT100」の取り組みがスタート
2018
- 2018年 6月
- 大阪北部地震が発生
2018
- 2018年 6月
- 地元企業の協力で小型店で買いもん行こカーが始動(稲美モデル)
2018
- 2018年 10月
- 神戸市と連携し「てまえどり(すぐに食べるなら手前からとってね)」運動をスタート
2019
- 2019年 2月
- 「プラスチック使用に関する基本方針」を策定
2019
- 2019年 5月
- 尼崎市と「『安心してくらせる地域づくり』に向けた包括連携協定」を締結。自治体との包括連携協定締結は初
2019
- 2019年 6月
- コープこうべコミュニティ宣言
2019
- 2019年 10月
- 全店舗で「てまえどり」の取り組みがスタート
2020

コロナ禍での生協の役割発揮
2020年2月、新型コロナウイルス感染症の拡大が顕著に表れました。4月8日に発令された「緊急事態宣言」を受け、外出自粛で店舗も宅配も利用者が急増。店舗は、開店から30分間を65歳以上の高齢者・障がい者・妊産婦優先の買い物時間としました。宅配では物流センターが許容量を超え、配達のトラックに商品が積みきれないなどの状況に。新規利用開始は2カ月待ちとなりました。組合員活動やイベント、コープカルチャー、コープスポーツは、おおむね6月末まで中止や休止としました。
その後も収束の兆しが見えず、インターネットを使った学習会やイベントが始まり、機関運営もオンラインでも開催することになりました。
2020
- 2020年
- 新型コロナウイルス感染症が拡大
2020

子どもたちの その子どもたちのために
2020年4月、「明石市おむつ定期便」の業務を受託。10月から、明石市内在住の0歳児がいる家庭に、毎月1回おむつ等の配達を開始しました。配達時に子育てに関する心配事などを聴くことで母子の見守り活動も行っています。
8月には、たつの市の「はつらつベビーまごころ便」の業務も受託し、配達を始めました。
2020
- 2020年 4月
- 「明石市おむつ定期便」の宅配業務を受託
2020
- 2020年 6月
- 「マイバッグ運動NEXT」がスタート。全店舗で買い物時のレジ袋の無料配布を中止。一部店舗では、家庭で不要になった紙袋を持ち寄り自由に利用できる「シェアバッグ」がスタート
2020
- 2020年 8月
- 「たつの市はつらつベビーまごころ便」の宅配業務を受託
2020
- 2020年 12月
- 聴覚障害のある人が買い物のときに意思を伝えやすくする「コミュニケーション支援ボード」を全店舗のレジに設置
2020

身近な行動が大きな゛うねり”に
2020年12月、第8回「食品産業もったいない大賞」の農林水産大臣賞(最高賞)を受賞しました。環境共生型農園エコファームの取り組みや、食品工場・店舗での廃棄ロス削減、フードドライブや「てまえどり」など、「組合員・地域と進める食品ロス半減」の取り組みが認められました。
2020
- 2020年 12月
- 「もったいない大賞」の農林水産大臣賞を受賞
2021
- 2021年 2月
- 「つながるマルシェ」の取り組み開始
2021
創業の精神に立ち返り、再出発
役員による接待に関する不祥事が発覚し、3月に対象者の役職の解職等処分を実施。第三者も含めた特別委員会を立ち上げ、再発防止にとどまらず、組合員の意見や職員の想いが政策に反映される組織の実現に向けた改革に着手しています。「愛と協同」という創業の精神に立ち返り、最も歴史ある生協としての自覚と責任を持って、次の100年に向けて再出発します。
2021
- 2021年 3月
- 創業の精神に立ち返り、再出発
2021

コープのあるまち 協同のあるくらし
創立100周年、同時に次の100年への扉をあけた2021年。「みんなが主役」を合言葉に、ビジョン「ターゲット2030(に・まる・さん・まる)」を策定しました。1万2300人の組合員・役員・職員の知恵と想いを寄せ合って、10年後の“ありたいまち・くらし”を表現したものが「ターゲット2030」です。
ここには、日本の協同組合の父であり、先駆者的役割を果たした賀川豊彦の言葉「未来ハ我等のものな里」の気概が今も息づいています。誰もが地域で安心してくらせるように、そして、未来の子どもたちが笑顔であふれるように。私たちは、これからもやさしい心で「コープのあるまち 協同のあるくらし」を実現します。
2021
- 2021年 4月
- コープこうべ創立100周年を迎える
2021
- 2021年 4月
- 認可保育園「コープこうべの保育園どんぐりっこすみよし」開設
2021
- 2021年 5月
- 「丹波篠山市における買物困難者等への支援に関する協定書」を締結
2021
- 2021年 5月
- 「お米を贈ろう助け合い募金」から地域団体に米を寄贈
2021
- 2021年 6月
- 第101期通常総代会後に100周年記念ソング「やさしさ つむいで」および「ターゲット2030」のキービジュアルとして「co・op vision」マークを発表
2021
- 2021年 7月
- 「CO・OP NEXT100開発商品」の供給開始(第1号商品「ほうれん草ちぎり」)
2021

「コープこうべ100周年のつどい」記念番組を開催
2021年7月11日、創立100周年記念イベントを開催。コロナ禍を考慮し、オンライン形式で実施しました。
この「100周年のつどい」は、2部構成とし、第1部は神戸芸術センターをキースタジオに、ビジョン「ターゲット2030」を宣言してスタート。100周年記念ソング「やさしさ つむいで」の合唱曲動画を披露した後に、早瀬直久さんとkimko(キムコ)さんによるポップバージョンの生演奏で盛り上がりました。
第2部は、コープこうべの8つの地区から、社会的課題の解決に向けて、地域とのつながりや協働を促進する生協らしい取り組みをリレー中継と録画で紹介。離れていてもつながりや交流を楽しむことができると実感したイベントになりました。
2021
- 2021年 7月
- 「コープこうべ100周年のつどい」記念番組を開催
2021
- 2021年 8月
- 高校生・高等専門学校生対象の奨学金制度がスタート
2021
- 2021年 10月
- 新ポイント制度がスタート。「コーピーカード」が誕生
2021
- 2021年 11月
- 新物流センター「見津が丘冷凍集配センター」が稼働
2022
- 2022年 1月
- 兵庫県の「官民連携による消費生活推進事業」を受託
2022
- 2022年 1月
- 神河町の福祉作業所と協働で高齢者の見守り活動をスタート
2022
- 2022年 3月
- 「ウクライナ緊急募金」を実施